こんにちは、かずMRです!!
このブログを読んでくれている皆さんの中には、
これからMRを目指す方や、まだ1~3年目くらいの方が多いかもしれません。
でも今回は、少し立場を変えて「後輩を育てる側」
──つまり、”指導する立場に立ったときにどうすべきか?”というテーマで書いてみようと思います。
私自身、気がつけば10年以上MRとして働いてきて、
チームリーダーとして新人育成に携わる機会も増えてきました。
「教えても伸びない…」「言っても動かない…」そんな悩み、ありませんか?
今回は、私が実際に後輩育成で意識しているポイント5つを紹介しながら、現場でのリアルをお届けします。
1. なぜ後輩育成が大事なのか?
経験談
そもそもなぜ後輩の育成が重要なのでしょうか。
これは実体験なのですが、
私が入社したころについていただいたメンターは運よく全国でも売上トップを毎年とっており、
周りからも時期マネージャーと期待されていた優秀な先輩でした。
対して、私の同期が最初に所属した営業所は万年ドベの営業所でパッとしない先輩(失礼)が多い営業所でした。
このあとのことは想像に難くないですが、その後のランクの上がり方がやはり全く違いました。
私は最速でMRとして最高ランクに到達したのに対し、
同期はほとんどランクも上がらず途中で他業界に転職していってしまいました。
入社当初はその同期のほうが明らかに目立っていましたし優秀で将来の出世頭とまで言われていたのです。
ここで言いたいのは、後輩の成長は育成者の質で決まるといっても過言ではないということです。。
チーム全体のパフォーマンスに直結
これも当然かと思いますが後輩の成長はチームを助けることになります。
これも実態件ですが、
私がチームリーダーになりたてのころオンコMRになりたての後輩が同じチームに配属されました。
最初は、慣れない環境に苦戦していましたが、
今となっては一番の戦力になっており、
同じチームの先輩たちに対してもものおじせずアドバイスまでするようになり、
私なんかよりも立派なリーダーではと思わせるほど成長し、チームをけん引してくれています。
このように、後輩を育成することはいずれ自分やチームを救うことになるのです。
上司からの評価にも関わる
私自身この考え方はあまり好きではないですが、
実際は関わってくるので書いています。
後輩育成を任されるような立場の人間は相当なベテランか将来管理職の候補だったりします。
この人にもし部下ができてもしっかりマネジメント・指導・育成ができるのか
この視点で見られていることは絶対に意識しなければならないのです。
2. 私が実践する育成5つのコツ
① まず“その人の強み”を早めに見つける
何はともあれ「観察」、
これが最も重要だと思っています。
後輩といえ十人十色、
- 「自分一人でじっくり考えるのが得意」
- 「あまり指示されたくないもしくは指示がないと動けない」
- 「とにかくチャレンジして失敗から学ぶ」
など様々なタイプが存在します。
例えば、自分一人でじっくり考えるタイプの人間にあれこれ指示を出して、
マイクロマネジメントしてもうまくいかないでしょうし、
チャレンジできる資質があるのに大事に研修ばかり受けさせてしまってはもったいないです。
最初はとにかく観察しその人のタイプを把握することが最重要です。
② 「正解」を与えすぎず、“考えさせる時間”をつくる
これはどうしても陥ってしまう人が多いのではないでしょうか。
私自身も最初の後輩が心配で心配でどうしても悩みに対してすぐ答えを見せてしまっていました。
でも今思うとこれもタイミングが重要なんですよね。
初めのころは答えをすぐに教えていいんですよ。
だって最初は大して考える引き出しを多く持っているわけでもないですし、
時間をかけて考えたところであまり良いアイディアは出てきません。
ただ、少し慣れてきたら「○○君はどう思う?」これを必ず差し込むようにしています。
後輩に頼りにされるとうれしくなってどうしてもすぐ答えを返してしまうんですよね。
でも、ある程度知識や考え方を伝授できたら、
今度は本人にそれを自分で扱う術を覚えてもらうのです。
そうすれは、自分のように考え行動してくれる分身の出来上がりです。
そして、自分すら超えていってしまうときは、なんだかうれしくなってしまいますよね。
③ 褒めるタイミングは“第三者を通じて”が効く
私は周りから、「後輩に厳しくない?もっと褒めてあげたら?」と言われます。
これは、冒頭に記載した私の最初のメンターを参考にしてるんですよね。
その方は私のことを直接褒めたことは多分1回もなかったのではないでしょうか。
でもある時、当時の上司から
「○○さんが言ってたんだけど、かずMRがあいつはガッツがあるし、
将来良いMRになりますよって言ってたぞ。良かったな。」
と言われたんです。
これは本人から言われる何十倍もうれしいですよ。
今思い出しても鳥肌が立つくらいうれしかったんです。
その時から、私も本人に直接褒めるのではなく第三者を通じて褒めるを意識しています。
直接褒めるとどうしても二人の関係にゆるみや甘えが生じてしまいます。
あと、やっぱり直接いうのは恥ずかしいですしね。
あと、第三者や評価者にしっかりその子の評判を広めることでその子の出世が早まることも感覚としてあるので、
このほめ方が一番その子ためになるのではと思っています。
④ 最初の3ヶ月は“とにかく伴走”してあげる
これが一番の味噌だと思っています。
後輩育成というとすぐに会議室でレクチャーを始めてしまう人がいます。
私はこれはすごくナンセンスだと思っています。
営業はまずは「現場」を見せることが何より重要だと思っています。
営業は人対人の仕事ですから、
実際に顧客と話しているところを見せてその時の
空気感、臨場感、間、タイミング、話法、ジェスチャーを学んでもらうべきです。
会議室でレクチャーばかりしている人を見ると、
「ああ、この人実際に顧客と話しているところを見せる自信がないんだな」と思ってしまいますし、
後輩もそう思っていると思います。
私は、失敗しているところを見せるのも教育の一つだと思っていますので、
とにかくどんな場所やシーンでも最初の3か月くらいは連れていきます。
⑤ 育成する側も“学び手”であることを忘れない
最後に、育成する側も”学び手”であることを忘れてはいけないということです。
教える立場にある人間が学びを辞めてしまえば、教わる側の成長速度も鈍化します。
何より、学び続けているその姿勢を後輩は必ず見ています。
尊敬している先輩から学べるほどうれしいことはないですからね。
3. 私が育てた新人のエピソード(実体験)
伸び悩んでいた後輩が変わった“ある一言”
一つだけ実体験をお話すると、
ある後輩は引っ込み思案で先生との面会もクロージングが弱く、
会議中もしり込みしてしまい中々発言ができない子がいました。
同行を繰り返したりして指導を続けてきたのですが、
なかなか性格までは人間変わりません。
そこでアドバイスしたのは「会議中、誰よりも早く、そして多く質問してみたら?」でした。
このアドバイスの意図としては、
質問を考えるということは相手の話を聞き深く考え自分の意見を考える手順が必要となりますし、
それを誰よりも早く考えることで負荷もかかり、
会話のトレーニングになると考えたからです。
すると、だんだんと会議での発言も増え、先生との会話もスムーズになり、
しまいにはクロージングもかなり得意になっていました。
実は、このアドバイスは昔私が先輩にいただいたアドバイスでした。
私もかなり引っ込み思案なところがあったのでこのようなアドバイスをいただいて多く改善できました。
逆にうまくいかなかったケースと反省点
逆に、指導する立場での反省点ももちろんあります。
最初のほうにも書きましたが、私はできるだけ第三者を通じて後輩を褒めるように意識しています。
しかし、それを意識しすぎるあまり、
後輩が「自分は褒められない。全然だめだ。」と落ち込ませてしまい、
怖い先輩だと思わせてしまったことがあります。
この時、指導する側の難しさを感じました。
その子に合わせた指導スタイルをどんどん身につけなければいけないんですよね。
4. 後輩を伸ばすには“信頼残高”の積み上げがカギ
でも結局は、すべて”信頼関係”があってこその指導です。
信頼関係が構築できていないのに、
指導されても聞く耳を持たれません。
アドバイスも心に響きません。
なので、私は最初はとにかく同行を推奨しています。
実際に長い時間を過ごし、お互いの人間性を知ることが後輩育成の第一歩だと思います。
今の時代嫌がられるかもしれませんが、同行の後、飲みに行ったり最低限昼食を一緒に取るなどもアリだと思います。
5. 最後に:育成は“自分自身を映す鏡”
後輩の成長は、自分の成長にもなる
人を育てるということは、自分を成長させることに通ずると思います。
後輩を指導する立場になり、
今まで先輩方からいただいてきたアドバイスの意味がより深くわかるようになったように思います。
これは立場が変わらなければ気づかなかったことだと思います。
読者へのメッセージ:「育成に悩んでる方へ」
冒頭にも書きましたが、人間は本当に十人十色で同じ人はいません。
なので育成方法も人の数だけあります。
そんな中、育成に悩んでいる人を私は尊敬します。
そもそも、育成することが評価に入ることはありますが、
定性評価で大したことはないはずなので別に本来頑張らなくても良いんですよね。
でも、そんな中で誰かを育成したいと考えるあなたには立派なリーダーになる素質があるのだと思います。
私も、まだ指導する立場になって間もないですので、
これからもたくさん学んでいきたいなと思っています。
まとめ
後輩育成は、誰にでも得意不得意があります。でも、少しの意識と工夫で大きく変わるものです。
この記事が、後輩の育成に悩んでいる方や、これからリーダーを目指す方のヒントになればうれしいです!
では、また!!
▼関連記事
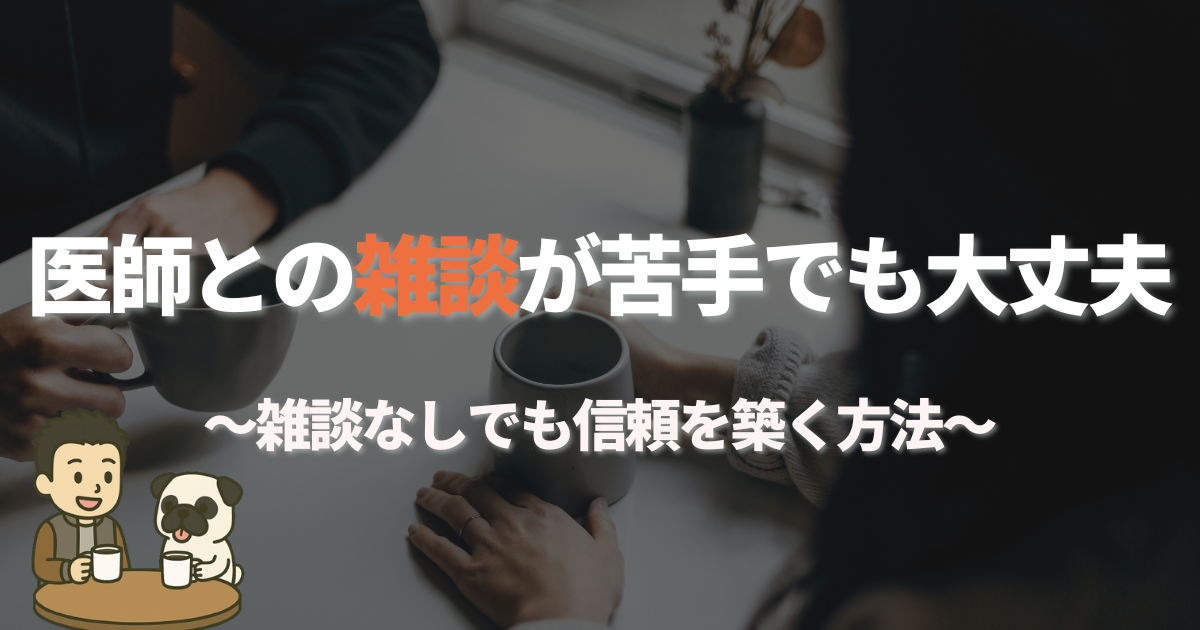
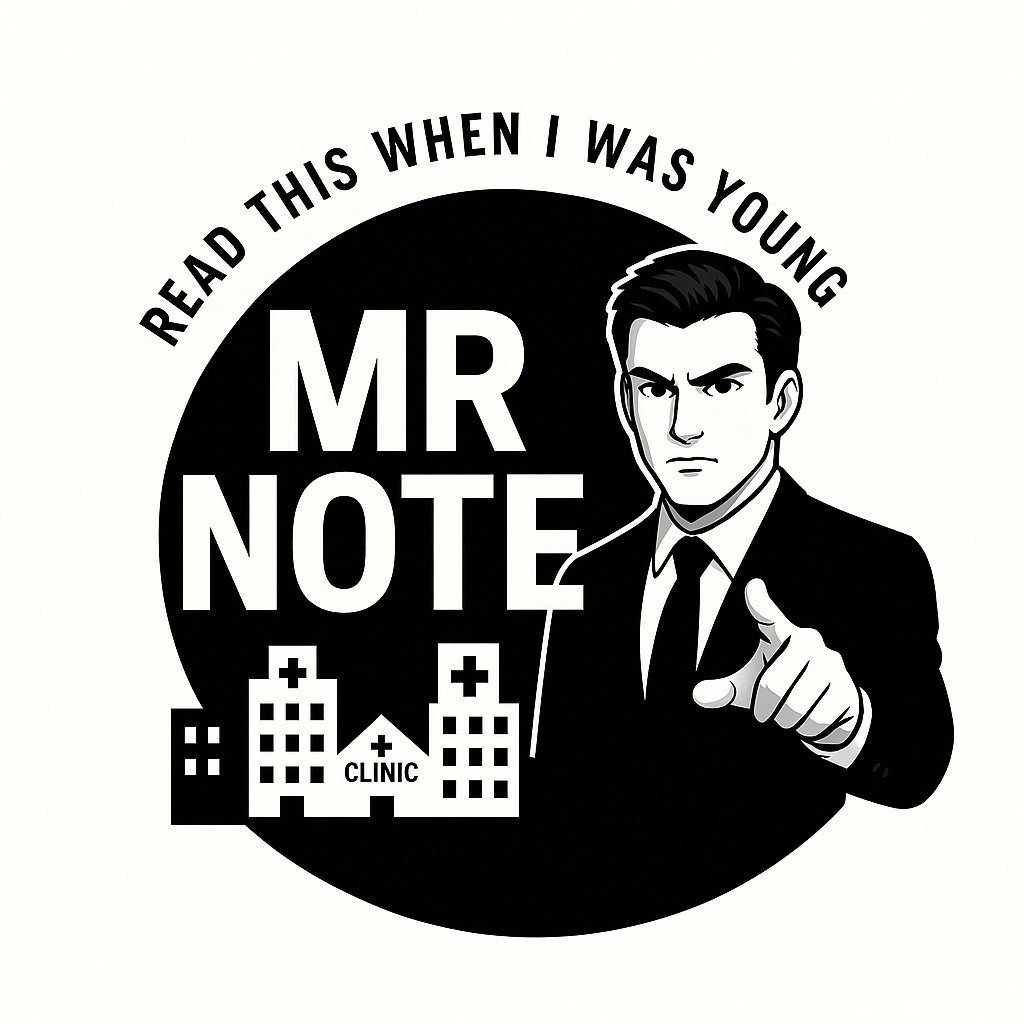
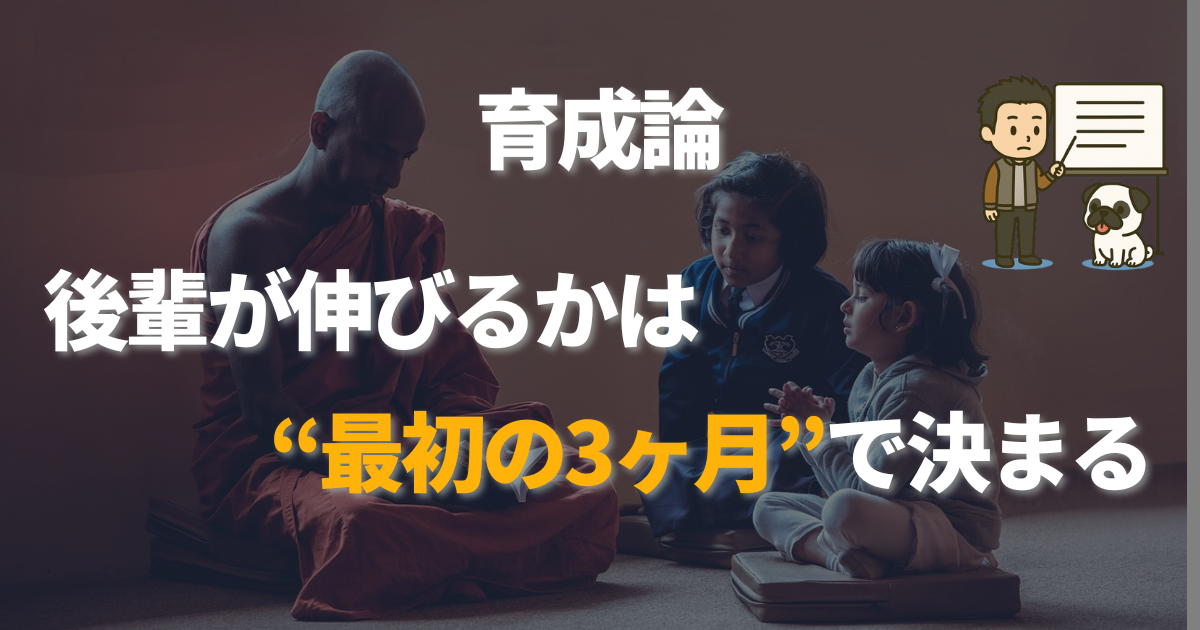
コメント