MSLって…何?
私は初めて大学病院を担当し始めたころ、前任から「MSLの○○さんがここの○○先生を担当してるから今度挨拶しようね」と言われてご挨拶したのが、初めてのMSLの方とのかかわりでした。
おそらく、開業医や中小病院を担当している方はまだMSLと積極的に一緒に仕事する経験は少ないのではないでしょうか。
皆さんが遅かれ早かれ一緒に働くことになるであろうMSLについて、今回は現役MRである私が実際に経験してきた「MSLとの付き合い方のリアル」をお伝えします。
あくまでも、MR目線ですのでMSLの方でこれは違うだろ!って部分がありましたら、ぜひコメントで訂正してください。
MSL(Medical Science Liaison)とは?
MSLとはメディカル・サイエンス・リエゾンの略称です。
その役割は、
製薬会社に所属する“医師向けの“非プロモーション領域の学術スペシャリスト”です。
簡単に言うと、「売らないけど、医師と対話して学術的な信頼を築く人」です。
実は、MSLって欧米では1960年代から存在する仕事で、かなり歴史がある職業なんですよね。
日本ではここ十数年で割と最近本格導入されてきたんですね。
 かずMR
かずMR初めてMSLを導入した会社はアップジョン社(現ファイザー社)らしいよ
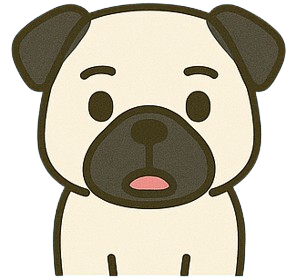
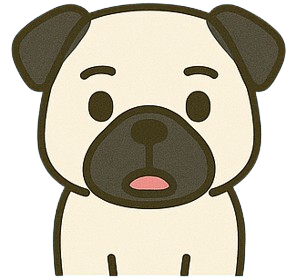
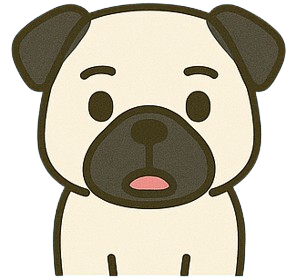
へー、知らなかった



MSLの重要性が高まったのが2011年前後の臨床研究の不正問題が契機となったといわれているよ
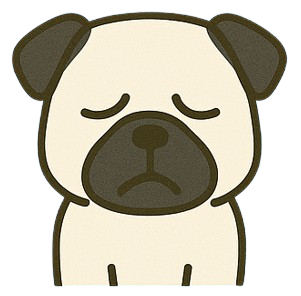
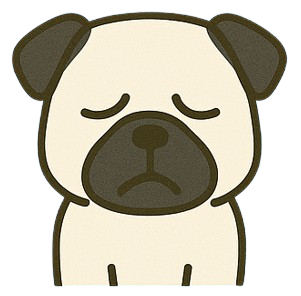
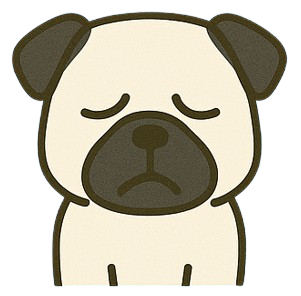
そのころからやたらコンプライアンスが厳しくなった印象があるよね
MSLが持っていることの多い資格・バックグラウンド
MSLに求められるのは、「医師と対等に議論できる学術的な素地」です。そのため、次のようなバックグラウンドの人が多いです:
| 資格・学歴 | 備考 |
| 博士号(PhD) | 理系・薬学・生命科学分野の研究経験者が中心。医師相手に科学的議論ができる |
| 修士号(Master) | 医薬・生物系で修士卒+研究経験ありの方も多い |
| 薬剤師(薬学部卒) | 特に日本国内では薬剤師免許保有者が一定数 |
| 医師・獣医師 | 一部企業では医師・獣医師がMSLとして活躍する例もあり |
以前までは結構営業経験者(元MR)もMSLに登用されるケースが多かった印象ですが、「博士号がなければなれない」のように条件が厳しくなってきている印象があります。
そして、彼らの学術知識にはいつも驚かされます。
「最近面白いネタなんかないですかね~」と軽く聞いただけで出てくる出てくる大量の情報が。
私の所属する会社では学術的にわからないところがあれば問い合わせをする窓口があるのですが、
そこではなく仲の良いMSLの方にいつも質問してしまっています。
MRとMSLの違い
では、改めてMSLとMRの役割の違いについて一覧にまとめてみました。
| 項目 | MR(医薬情報担当者) | MSL(メディカル・サイエンス・リエゾン) |
| 主な目的 | 製品の適正使用促進(営業活動) | 学術的対話を通じた医師との関係構築 |
| 売上目標 | あり | なし |
| 対応する医師 | 施設全体・幅広い層 | 主にKOL(Key Opinion Leader)など学術志向の強い医師 |
| 話す内容 | 製品説明、講演依頼、講演会案内など | 論文、疾患領域の最新情報、臨床試験など深い学術情報 |
| コンプライアンス | プロモーションルールに沿った説明 | 非プロモーション、科学的中立性重視 |
かなりざっくりと分けてみましたが、こんな感じでしょうか。
MSLが現場で果たす役割(現役MR視点)
MSLの主な業務は、医師と以下のようなやり取りを行うことです:
MSLの主な役割(現役MR視点でまとめ)
- KOL(キーオピニオンリーダー)との学術的な関係構築
┗ 論文・ガイドライン・最新エビデンスを軸にしたディスカッションを実施 - 医師主導研究(IIT)の相談・支援窓口
┗ 研究テーマの相談対応、社内調整、資材や資金提供のハブ - 臨床現場での“エビデンスギャップ”の発見と社内共有
┗ 現場の課題や未解決ニーズを社内メディカルや開発部にフィードバック - 治験・自社臨床研究への科学的支援
┗ 実施施設のマッチング、医師対応、データ発表サポートまで伴走 - アドバイザリーボード(KOLを集めた意見交換会)の企画運営
┗ 専門家の声を社内戦略に活かすための会議体を設計・実施 - グローバルメディカル部門との情報連携
┗ 海外の最新知見や医療戦略を日本市場へ共有・調整 - 非プロモーション情報(適応外・安全性等)の提供対応
┗ 医師からの要請に応じて、ガイドラインや学会情報に基づく科学的回答を提供 - 社内向けの疾患・製品研修の講師役(企業によって)
┗ MRやマーケ部門向けに疾患啓発・最新文献レビューを実施する場合も
MRとして現場で感じるのは、「MSLが来るだけで医師の表情が変わる」瞬間があることです。
営業トークではなく、“自分の研究や診療と向き合ってくれる存在”として、
医師にとってMSLは特別な存在に見えているのだと思います。
MRがMSLと連携する意味
前置きが長くなってしまいましたが、ここからはMRとMSLの連携について書いていきたいと思います。
MRがMSLとうまく連携できると、次のようなメリットがあります:
- 学術的に信頼される情報を届けられる
- 医師との関係が一段深まる
- 社内(メディカル、マーケ)との橋渡しができる
- 自分だけでは到達できなかったKOLとつながれる
つまり、MSLを「社内の味方」として活用できるかどうかは、MRの営業力を飛躍的に高める鍵になります。
私の実体験で、新たに新薬が発売されることになったのですが、
担当病院で全国的にも有名なKOLがいたのですが、
今まで持っていた製品とは全く関連のない領域のDr.だったためコンタクト方法すら不明でした。
しかし、MSLは発売前に事前にアドバイザリーボードや社内向け研修で先生とはすでに深い関係構築ができていました。
なので、わたしはその担当MSLの方に頻回に同行してもらい、MRとKOLの関係も作ってくれました。
MRも医師と会社をつなぐ媒体と表現されることが多いですが、
MSLも同様に様々な人をつなぐ働きを持っているんだなと実感したのを覚えています。
「この先生はMSL案件だ」そう思ったら、最初にやるべきこと
KOLクラスの先生と向き合うとき、「これは自分だけじゃ情報が浅い」と感じる場面があります。
そんなとき、私はまずMSLの顔を思い浮かべます。
ただし、安易に「MSLに同行してもらおう」ではうまくいきません。
私がやっていたのは、医師のパーソナリティと好みの共有”です。
たとえば——
「この先生、深い議論は好きですが、脱線しがちなので、テーマは1本に絞った方がいいです」
「副作用の話題にはかなりナーバスなので、論文ベースで安心感を持って話してもらえるとありがたいです」
「今先生の抱えている課題(テーマ)は○○なんですけど、何か解決する糸口はありませんか?。」
こういった“現場の温度感”は、MRだからこそ伝えられる部分です。
MSLがその空気をつかめるかどうかで、面会の成果は変わります。
MSLはMRより先生との面会数自体は少ないことが多いので現場の情報はできるだけ多く伝えておくこと。
これが、MSLの方との良好な関係を作る第一歩だと思います。
お互いの仕事にリスペクトを忘れずに
私がこれまで一緒に仕事してきたMSLの方々は、皆さん学術的に誇りを持って仕事をされています。
その一方で、営業サイドがその部分をしっかりと理解せずに営業側の期待ばかりを押し付けては、
失礼になってしまうこともあります。
例えば、
○○薬をどうしても使ってほしいから、自社にとって良い○○文献を紹介してほしい。
そもそも、MSLと非プロモーションを前提としていますからね。コンプラ的にもアウトです。
同行をお願いするときも、
- 訪問の背景
- 医師の課題意識
- 面会の目的(疾患?薬剤?講演会の布石?)
こういった医師やMR側の考えていることをしっかり整理して伝えるようにしています。
MSLの方も行ってみたら全然先生が求めてる情報も状況も違うとなってしまうと
次回はMSL単独訪問でいいかとなってしまいますからね。
※同行の際、MSLが話すときはMRは原則退出します。
トラブル対応の“前線”に立てるかどうか
あるとき、MSLが面会中に医師の機嫌を損ねてしまったことがありました。
MSLの中には営業経験がない人も最近では多くなってきてます。
いくらMSLとはいえ相手から見れば製薬会社の一社員ですので、失礼があればそれは怒ってしまうのも致し方ないです。
私はその場で会話を切り替え、MSLに一歩引いてもらいながら、先生の表情を戻すようフォローに入ったり、
すぐに上長に状況を説明し一緒に謝罪に伺ったりします。
こういう時、「MSLがやらかしたから自分は知らない」ではなく、MRが前線に立てるかどうかが信頼を分けると実感しました。
一緒にKOLと向き合う“チーム”になるまで
信頼が築けてくると、KOL対応の初期設計からMSLと一緒に相談できるようになります。
「今回の面会は、今後の講演会のテーマ決めを兼ねてます」
「先生が最近ハマってるのが●●論文なので、それを軸にしたディスカッションができると面白いかも」
MSLのほうから「じゃあ、その内容で社内のメディカル部門と確認してみますね」と返してくれるようになると、
最強タッグの完成ですね。
MSLとの関係性で、大学病院での仕事の質が決まるといっても過言ではないと私は思っています。
まとめ|MSLとの関係は、距離感と敬意のバランスで決まる
MSLとの関係構築は、簡単ではありません。
でも、適度な距離感と敬意をもって向き合い、丁寧に積み重ねていくことで、確実にチームになれると私は感じています。
お互いの立場を理解し、情報を先回りして共有し、医師とのやり取りをプロデュースする——その繰り返しの中で、「MSLと一緒に成果を出す」という私の営業スタイルが生まれました。
MSLの方とどうやって協力していけばよく分からないという方は、今回の記事で少しでもMSLの理解が深まり、協力し合える関係になれることを願っております。
今度は、MR目線から見たマーケティングの方との付き合い方についても書いてみようかと思います。
では、また!
▼関連記事(あわせて読みたい!)
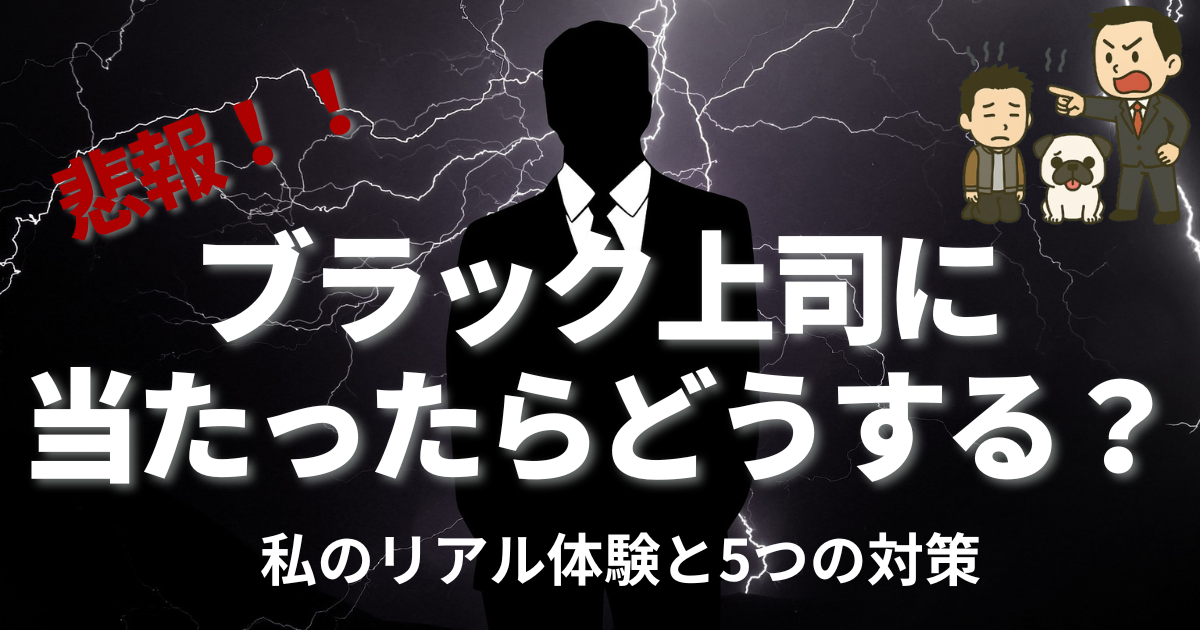
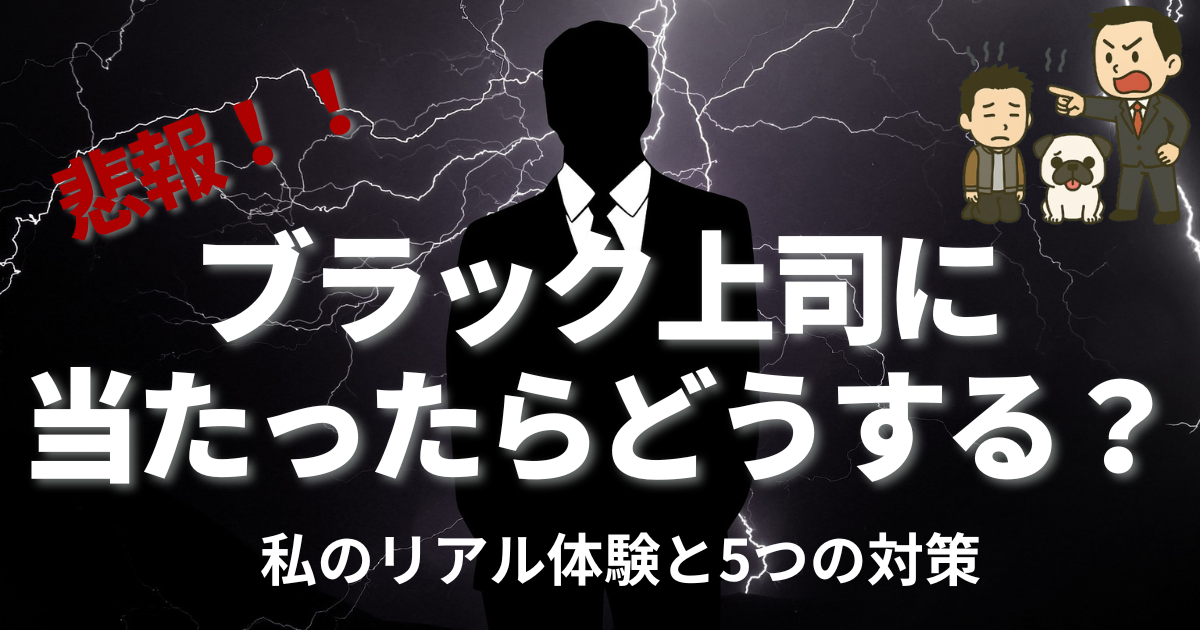
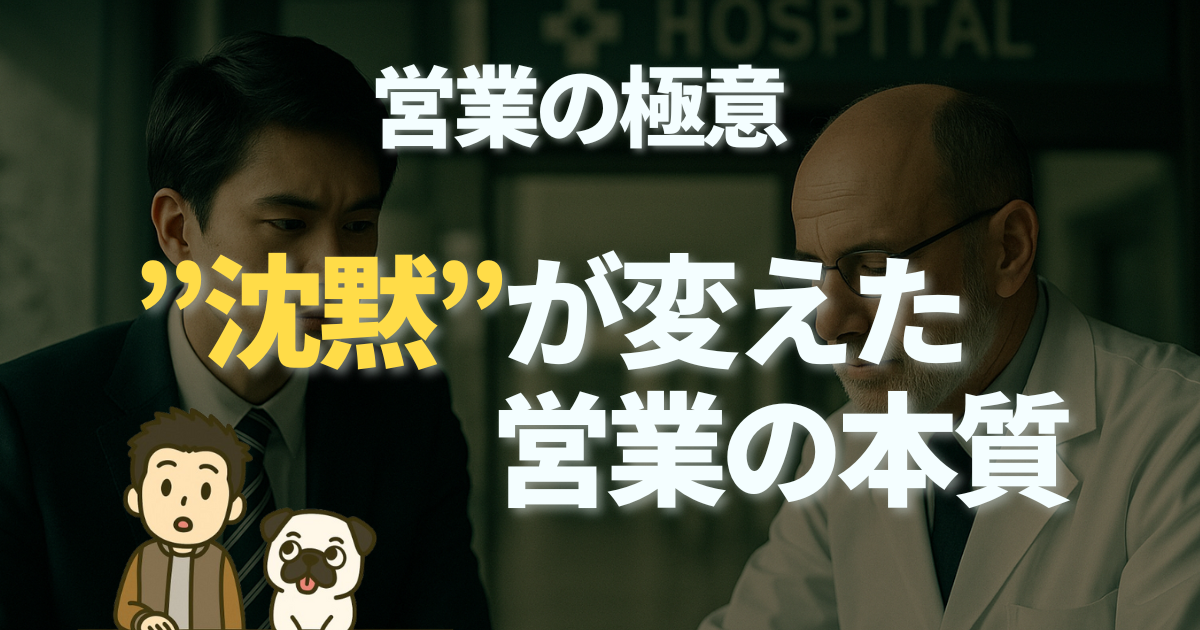
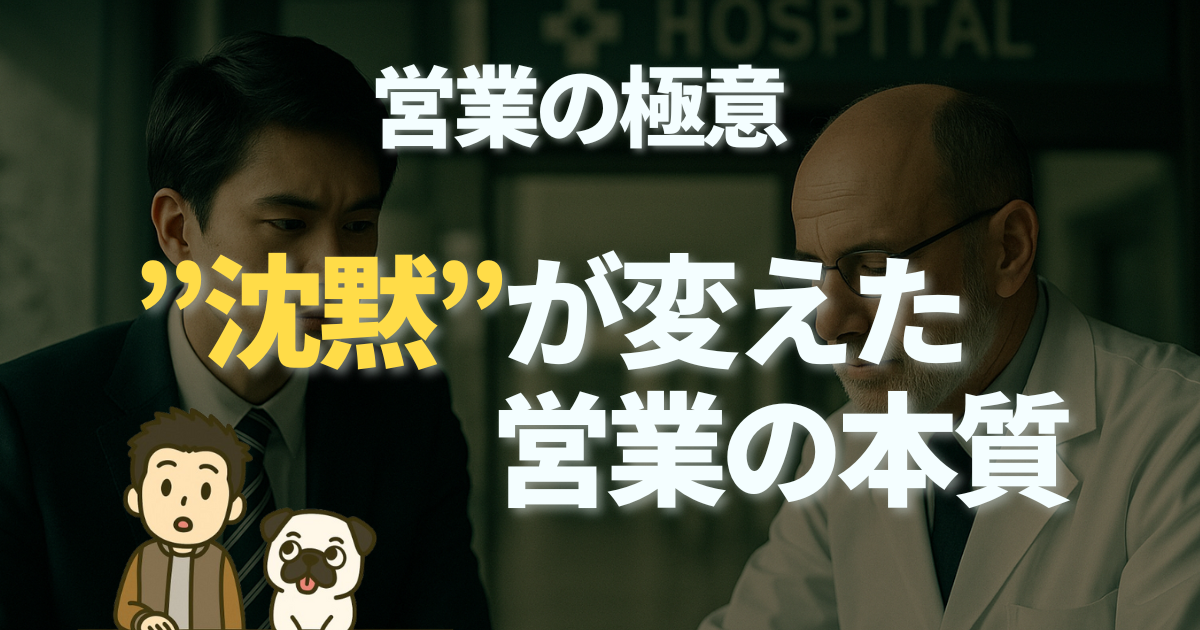


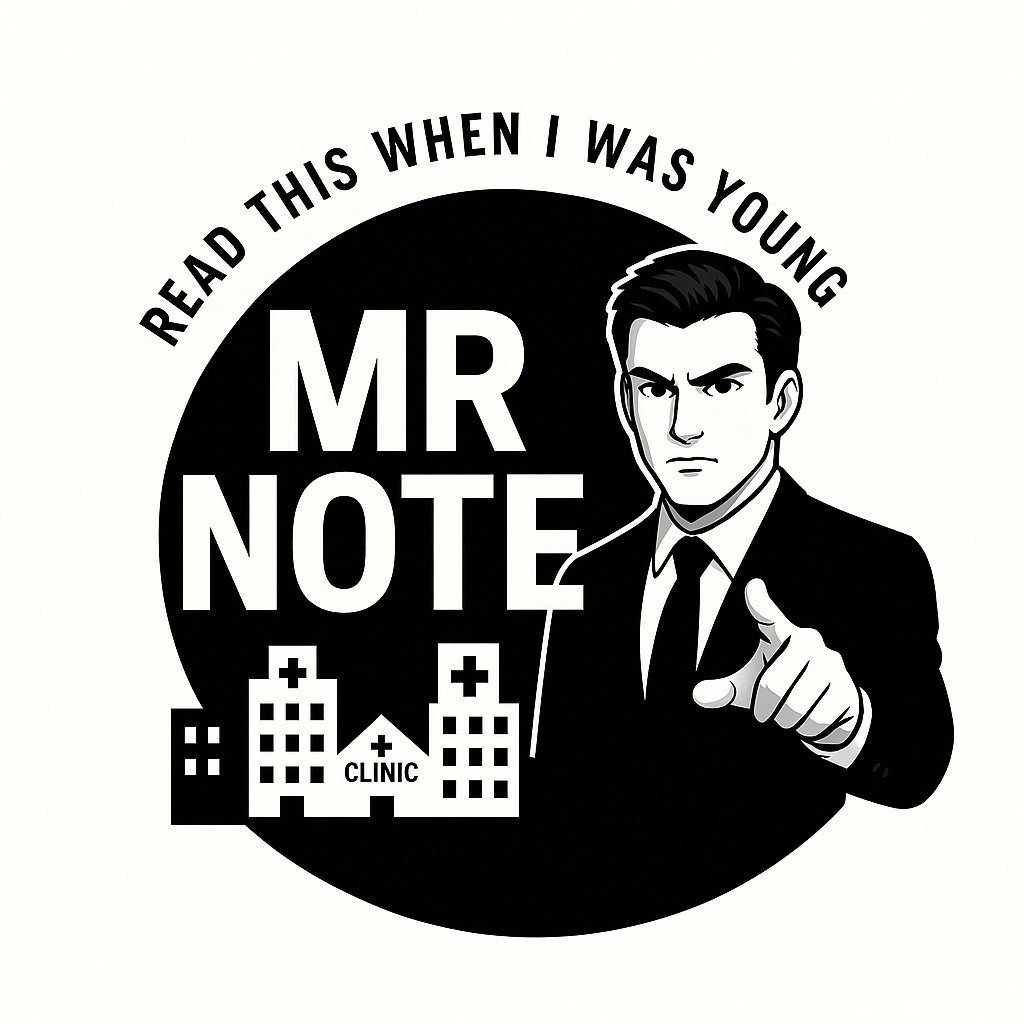
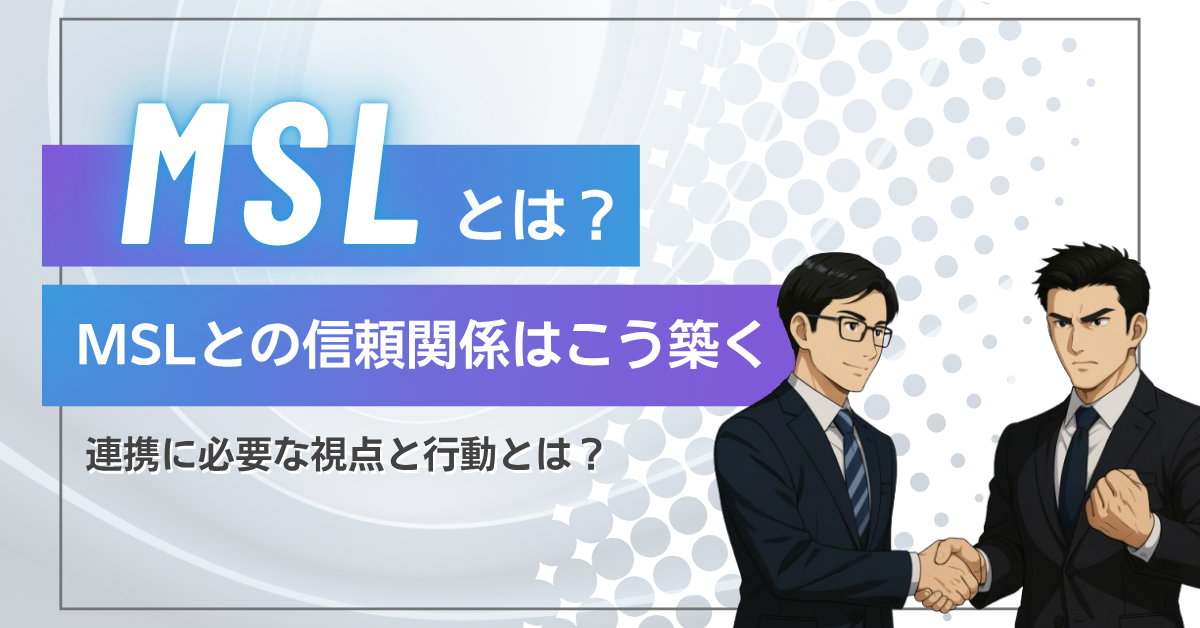
コメント